 
第3話(その1)
3
人類の歴史において、国の興亡とそれに伴う戦争は絶えたことがない。主義・主張の対立、一個人による野心、理由は様々であるが、互いに掲げる大義名分は他者の存在を否定し大いなる闘争を引き起こす。
千年帝国とクレティナス王国は建国の当初から対立していたわけではない。クレティナスの成立は宇宙標準暦一三○九年にさかのぼるが、ここ一・二年を除く二五三年の歴史の中で両者の間には対立の記録は存在しない。近年の抗争は千年帝国にすればクレティナスによる侵略行為と映っていたが、クレティナスにしてみれば千年帝国は二○○年にも及ぶ銀河の戦乱をつくった張本人であり責任を取るべき相手であった。
王都星フェリザールを発進したクレティナス王国軍第四九艦隊はユークリッド・タイラーの待つ千年帝国軍要塞「バルディアスの門」を目指すべく宇宙をひた走っていた。王国軍司令部の公式文書、及び隣国大使に対する外交文書の中に第四九艦隊の行動は記されていない。自由艦隊という性格上艦隊の行動はすべて事後処理的に作戦終了後に公式文書に載せられる。よって、現時点での四九艦隊の行動は、非公式なものであった。
艦隊はゆっくりと進んでいた。実際は光の速さにも迫る超高速で動いているのだが、大宇宙の広さの中では遅々たる動きにしか見えない。悠久なる時間の流れは、人の小さな営みのすべてを包み込んでいた。
アルフリート・クラインは宇宙が好きだった。人の魂を縛る重力から解放されて、無限の大きさを感じる宇宙に身を委ねると、この世のしがらみをすべて忘れることができたのである。歴史を取り戻せと言い残して死んでいった父のことも、主君に奪われた恋人のことも、そして、彼を待っている千年帝国の名将ユークリッド・タイラーのことも、すべて小さなこととして忘れられた。それゆえに彼は思うのだ。宇宙に身を任せた者にとって、国家だとか信念だとかいったものは何の価値もないものだと。
宇宙のなかの人間はあまりにも小さい。その小さな存在がいくつにも分かれて二○○年にも及ぶ戦争を続けている。なにゆえに人は戦うのだろうか。
静寂の時間が過ぎていった。
新しく第四九艦隊の旗艦となった戦艦「飛龍」の作戦会議室でアルフリートは副官が運んできたコーヒーに口をつけていた。つい先刻まで、艦隊副司令官ベルソリック准将や分艦隊司令官グエンカラー准将、ブラゼッティ准将といった艦隊の首脳を集めて「バルディアスの門」攻略の作戦を論じていたのだが、彼らが自分の艦に戻るのを待って一息つくことにしたのだった。
「なかなかすばらしい人材だな、彼らは」
将官達が去ったあと最後まで残っていたファン・ラープ准将にアルフリートは語りかけていた。四九艦隊が創設されてからファン・ラープはいつのまにかアルフリートの腹心のような立場になっていたのである。
「ええ。特にベルソリック准将は理論だけでなく実際の指揮の方も優れたものがあるといいます。閣下に対する私の地位も少し危なくなってきましたね」
「ハハハ、おまえはあいかわらず自信過剰だな。自分の能力がそんなに高いと思っているのかい」
本心では結構ファンのことを評価しながらもアルフリートは笑った。
「閣下は人が悪いですね。まだこの間のことを根に持っているのですか」
この間のこととは、四九艦隊創設時の仕事が忙しいときに、ファンがさぼって街へ遊びに行ってしまったことである。翌日、軍のオフィスビルに戻ったファンはアルフリートの苦情を一時間も聞かされたのだった。
「そうかも知れないな」
アルフリートの意地の悪い返答にファンは苦笑するしかなかった。
戦場まではまだかなりの時間があった。今回の遠征は直接「バルディアスの門」を突く作戦ではなく、クレティナス軍の最前線基地であるヴィストゥール要塞を経由して、そこで作戦に必要な物をそろえてから「バルディアスの門」に向う予定だった。
アルフリートの頭のなかには、「バルディアスの門」攻略の青写真が明確に描かれていた。「流れ星」と名付けられた作戦である。現在、第四九艦隊のなかでその作戦の内容を詳しく知る者はアルフリートをのぞいて四人しか存在しない。艦隊首席幕僚ファン・ラープ准将とベルソリック、グエンカラー、ブラゼッティの三人の司令官であった。
最初、この流れ星作戦を打ち明けられたとき、ベルソリック、グエンカラー、ブラゼッティの三人は驚愕の声を上げたものだった。
「何という作戦だ!戦術や戦略といった次元を越えている」
三人は沈黙し、長い間彼らの若き司令官をじっと見ていた。
「……成功すると思いますか?」
間を置いて言葉を発したのは光沢のある金髪と鋭い眼光の所有者であるオスカー・ベルソリック准将だった。
「させるさ。失敗など考えていない」
アルフリートの返答は短いものだった。しかし、その時ベルソリックに向けられた彼の瞳には、誰にも妨げることのできない強い意志が存在していた。
「……恐ろしい人だ。私は正直、閣下のような人を敵に回さなくて良かったと思います。この上は非才な身ではありますが、私の持てる力のすべてを尽くしましょう」
アルフリートは作戦の実行に際して三人に重要な任務を与えていた。それは、ヴィストゥール要塞で受け取った土産を「バルディアスの門」に届けるという聞く分には単純なものであったが、実行にはかなりの困難を伴うものだった。しかし、彼ら三人ならば必ず成功させてくれるだろうとの確信に近いものをアルフリートは持っていた。
三人より先にアルフリートの作戦を聞かされていたファン・ラープは上官にならってコーヒーを口に注いでいる。出征中ということで大好きなアルコールを飲むわけにはいかなかったが、彼なりに状況を楽しんでいた。
「それにしても……、閣下は本気でおやりになるつもりですか」
ファンはアルフリートの意志を確認するように尋ねた。
「要塞を破壊してしまうことかい」
「そうです。帝国軍はあの要塞を建設するのに二○年を有したといいます。彼らも労力を無駄にされては浮かばれないでしょうね」
流れ星作戦の真意は要塞攻略にはない。本来、望ましいのは「バルディアスの門」要塞を攻略占領し、それをクレティナス軍の帝国に対する侵攻の橋頭堡とすることである。しかし、現実的に考えて神将タイラーの守る要塞を無傷の状態で手に入れるのは不可能なことと言えた。
「そうだな。しかし、たとえ破壊してしまっても何の価値もないものだと私は思うね。要塞なんて物は本来自由なはずの宇宙の道を閉鎖し、戦争をするためだけに存在しているんだ。人類全体の利益を考えたら、ない方がいいに決まっている」
「閣下はあまり軍人らしくはありませんね。もちろん、私とは違う意味においてですが」
「私もそう思うよ」
アルフリートはファンの言葉にうなずいていた。
|
 |
  |
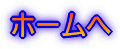
|

